令和三年(2021)七月十九日、羽田空港からANA4777便で、女満別空港に向った。
ANA便は、すべてAIRDOの運行便になっているため、
ワイファイが使えないのは残念だったが、
その他はANAと変わらないサービスであった。
空港に着くと、レンタカーを借り、天都山オホーツク流氷館に行く。
水族館では、クリオネの水槽で、クリオネを間近で見て、
北海道で最大級のプロジェクションマッピングを楽しんだ。
マイナス15度の流氷体感テラスには、本物の流氷が100t展示されていて、
夏の訪問ではしばし涼しい体験が出来てよかった。
 |
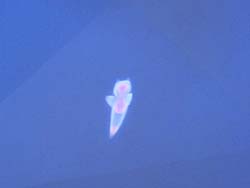 |

| ||
流氷館を出て、かって、網走刑務所であったところに向う。
坂を下ると、博物館網走監獄がある。
「 網走刑務所は、昭和五十八年(1983)、
新しい建物に全面改築されることになった。
旧建物は歴史的に価値があると判断され、
一部の建物が残され、昭和五十八年(1983)に、網走監獄博物館として開館した。 」
鏡橋を渡ると、入館受付があり、一人千百円を支払い、中に入る。
入館受付の右側に正門がある。
説明板「二見ヶ岡農場旧正門」
「 明治24年に始まった中央道路開削工事などの、外役労働が終わり、
網走刑務所が自給自足による農業監獄を目指して、本格的な開墾が始められました。
明治29年には、現刑務所から西方6kmの二見ヶ岡に外役所が設けられて、
やがて、日本一広大な刑務所農場(16,181,266㎡)がつくられました。
この門は、博物館に移築復原されている、二見ヶ岡農場の正門を再現したもので、
博物館網走監獄の入場ゲートとしたものです。 」
この門前の右側に、「映画監督・石井輝男の作品 「網走番外地」 のシリーズは、
網走刑務所を舞台に作られた。
石井監督の墓は、網走市内潮見墓園にある。 」と、
書かれた、赤御影石の碑が建っている。
中に入ると、正面に、赤い煉瓦のおしゃれな門がある。
説明板「煉瓦門」
「 明治23年、網走外役所創設当時と、明治42年の火災焼失後復旧した正門と外塀は、
木造でした。
これを永久的な物にするため、明治45年に用地内粘土で、煉瓦の製造をはじめ、
大正8年から5年かけて、築造しました。
これが、今も、網走刑務所の象徴となっている、「赤門」と呼ばれる正門です。
高さ4.5m、全長1,086m、使用した煉瓦は150万枚で、
基礎石や塀の上の笠石も用地内から採掘した軟石を用いています。
この意匠は、日本近代建築初期のものとして、重要視されています。 」
門前には遠くから見ると本物と勘違いする人形の看守が立っていた。
門側に立って、看守が不審者が入らないように、勤務していた様子を再現している。
 |
 |

| ||
正門の中、右側に看守控え室があるる。
悪天候の日や、記録簿に記入する時などに、この部屋で執務が行われた。
門をくぐると、刑務所の歴史を紹介するコーナーがある庁舎の建物がある。
この建物は、国の重要文化財に指定されている。
説明板「旧網走監獄 庁舎」
「 本建築にみる紋章入りの破風をのせた正面車寄せ・押し上げ式の窓・
木造下見張りは、明治10年前後、学校や官公庁の建築にみられた様式で、
和洋折衷の 「擬洋風建築」 といわれています。
この旧網走監獄庁舎は、明治42年の火災後、同45年に再建されたもので、
網走監獄の管理棟として、使用されていました。
昭和63年10月、博物館網走監獄に移築保存されました。 」
庁舎を出て、案内マップを見ると、味噌・醤油蔵や、釧路地方裁判所網走支部法廷・
二見ヶ岡刑務支所などの色々な施設を見学するルートになっている。
それらを見ると1時間半以上もかかるので、訪問はあきらめた。
帰り道になる右側の道に出ると、独立型の独居房があった。
説明板「煉瓦造り独居房」
「 明治時代、監獄内の規則を守らない者には食事の量を減らし、
一定の期間、生活させる罰がありました。
窓のない真っ暗な、この独居房での生活は受刑者にとって、大変つらい生活でした。
この煉瓦造り独居房は、明治末期に造られ、平成3年3月に博物館網走監獄に移設されました。 」
 |
 |

| ||
その先の右奥には浴場があり、その中に、 囚人の浴場風景が人形で再現されている。
説明板「浴場」
「 大勢の者が寝食を共にする刑務所では、皮膚病などが流行しやすく、
そうした衛生面からも、浴場は欠かせない施設のひとつで、
且つ、1日の作業終了後、受刑者にとって入浴は楽しいひと時でした。
網走刑務所では、「差湯方式」 の浴場が、明治42年の大火で焼失後、
コンクリートの浴槽に、蒸気で湯をわかす当時では、まことに近代的な浴場でした。 」
浴場の外に、煉瓦壁の一部が置かれていた。
説明板「網走刑務所赤煉瓦外塀の煉瓦」
「 この煉瓦は、現刑務所の外塀に使われていた煉瓦の一部で、
最近、工事用出入口を造るために、取り壊されたものです。
布コンクリートの上に、敷石の基礎石を敷き、
その上に、煉瓦を3丁3段積みから、最上部は1丁半積んで、
更にその上に、1尺巾(30cm)の笠石を置いたつくりになっています。 」
 |
 |

| ||
坂を登りきると、右手に移築された旧網走刑務所の中央見張所と、 それを中央にした五つの監獄が建っている。
説明板「旧網走刑務所 舎房及び中央見張所」
「 この舎房は、明治42年の火災で焼失後、それまでの並列型の舎房に代わって、
同45年に再建された、放射状の旧網走監獄 舎房です。
中央見張を中心に、雑居房・独居房・鐙格子・矢筈格子といった、
独特の建築技法を採用し、昭和59年9月まで、使用されていました。
明治時代の獄舎の名残を完全にとどめる舎房としては、
国内最大規模で、ことに木造は現存する我国最北端の監獄として、
学術的に貴重なものとされています。 」
中に入ると、放射状に伸びる五つの舎房の手前に、八角形の中央見晴がある。
「 放射状に伸びる五つの舎房を一ヶ所から、 監視できるように、八角形の見晴所が設けられている。 」
 |
 |

| ||
網走監獄のこれらの建物は、昭和六十三年(1983)まで、 約百年に渡り使用されていた舎房で、国の重要文化財に指定されている。
「 ここには、独居房・雑居房合わせて、226房あり、
最大700名を収容できました。
舎房の廊下には天窓がつけられおり、クイーンポストトラスの小屋根と、
鉄筋の開き止めが、美しい空間を造り出しています。 」
第三舎は、雑居房で、総数三十二。 雑居房の広さは九・九〇六平方米で、
数人で起居していた。
部屋の中には棚があり、入口には木製の格子がはめられ、
その上には、鉄製の格子がはめられていた。
第四房は独居房で、80房があった。 部屋の広さは4.90㎡であった。
この建物を進むと、小屋根の下の三角テラスに、
裸の人形が屋根に向う様子になっている。
これは脱獄再現シーンである。
第四舎第24房に収容されていた、白鳥由栄は青森刑務所・秋田刑務所・網走刑務所・
札幌刑務所と、四回脱獄したつわものである。、
秋田では収監された鎮靜房の天窓の釘が腐りかけていることに気付き、
布団を丸めて立て、よじ登って脱獄。
網走では、味噌汁で手錠と、視察孔の釘を錆びさせ外し、関節を脱臼させて、
室外に出て、天窓を頭突きで破り、煙突を引き抜いて脱獄。
時は第二次大戦の昭和19年。
札幌では、隠し持った金属片で鋸を作り、床板を切断、食器で床下にトンネルを掘り、脱獄。 」
 |
 |

| ||
中央見張所を出て、来た道を引き返す。
先程の煉瓦造り独居房を過ぎると、左側に教誨堂がある。
この建物は、国の重要文化財に指定されている。
「 教誨(きょうかい)とは、僧侶、牧師などの宗教者が刑務所を訪れ、
受刑者に人の道を説き、犯罪ですさんだ気持ちを和らげ、
更生へと導くことを言います。
明治45年(1912)建築の材料も、作業で山から切り出した木を使って作りました。
瓦も、網走監獄の窯で焼いたものです。
宗教的な意味合いがある建物ですので、
「神仏の魂を宿す建物だ」 と、特に精魂込めて作ったといわれています。
戦前(1945年)まで、網走の教誨事業は、
仏教の浄土宗東本願寺派の宗派が行っていたので、
正面には仏壇をこしらえ、阿弥陀如来像を安置していました。
戦後は舞台に改造し、多目的に使えるようにしました。
昭和56年(1981)に移築復原し、平成17年(2005)国の重要文化財に認定されました。 」
出口手前右側にあるのは、哨舎である。
「 これは、外部からの侵入や受刑者達の行動を監視する見張所のことです。
明治13年に内務省が制定した図式に基づいて、
全国各地の刑務所では、出入口に様々な色や型の哨舎を設けています。
この哨舎は平成5年まで、実際に網走刑務所で使用されていたものを移築したものです。 」
 |
 |

| ||
訪問日 令和三年(2021)七月十九日